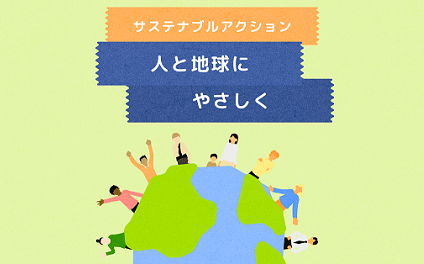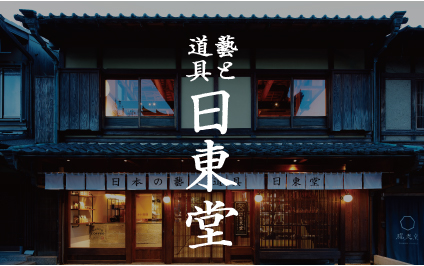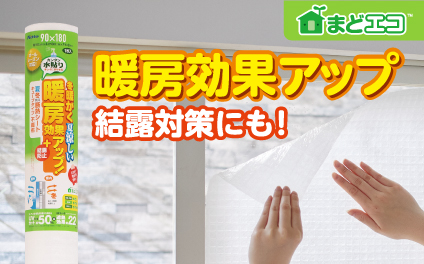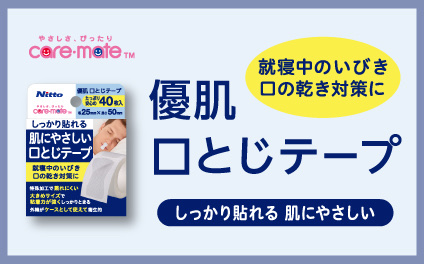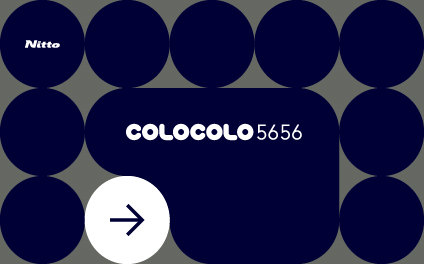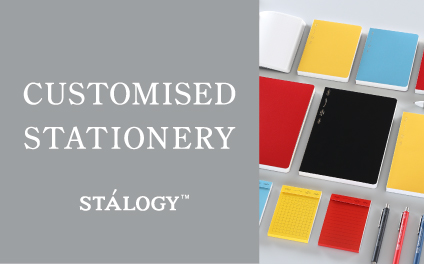ニトムズ
INNOVATION
FOR
CUSTOMERS
カテゴリから探す
お知らせ
- 製品・サービス
- 日本屈指のデザイナーとのコラボレーション 上質なデザインと書きやすさを追求 『低粘度油性ボールペン クラシック 0.5mm』新登場
- コーポレート
- お客様相談室 ゴールデンウィーク休業のお知らせ
- 製品・サービス
- 【ムーミン×STALOGY】キャラクターとのコラボレーション製品が初登場 繊細な手描きタッチの「ムーミン」の挿絵を採用した文房具を発売
- 製品・サービス
- 力強い筆遣いが人気の画家・イラストレーター 林 青那氏の作品を起用 京みやげにぴったり 店舗オリジナルの風呂敷・ノート
- 製品・サービス
- 自由自在に貼ってはがしてタスクを管理 2サイズ展開の『貼ってはがせる To Do シール』
- 製品・サービス
- ズレる、のり残りが心配、洗濯時に手間がかかる、「3つの困った」を解消 床からキレイにはがせる カーペット固定テープ